三大稲荷の一つ、茨城県にある笠間稲荷神社。
稲荷神社といえば、おいなりさん(いなり寿司)!
ということで、参道に売っているいなり寿司を買って食べてみると、めちゃくちゃ甘かった。
そして、胡桃が入っていた!
もしやおいなりさんって、地域によって全然違うアレンジなのでは?!と気になったので、この記事では笠間のいなり寿司についてご紹介する。
狐だらけ

毎年菊まつりを開催している、笠間稲荷神社。
今年初めて訪れたのだけれど、とにかく狐がたくさんいる。
大きな鳥居の両サイドに狐。(「鳥居」と「サイド」という言葉のコンビネーションが悪い気がする。両端とかの方がしっくりくるかも。)
露店には狐の形をした置物やおみくじ、手で色付けをしてある狐のお面。
神社の後ろには、狐塚(きつねづか)まであった。
狐が好きだ

私は昔から狐が好きだ。
まず「狐」という漢字からしていい。
媚を売ってなくてすらっとしていて、ミステリアスで妖艶である。(そう思うのは私だけ?)
小さい頃読んだ本やマンガには、よく狐が出てきた。
目が細くて吊り上がっていて、頭が良くて、何を考えてるかわからない、ちょっと意地悪なキャラクターであることが多い。
特に、『町でうわさの天狗の子』というマンガに出てくる狐がお気に入りで、この狐はなんとも色っぽいのである。(人型にも変身するのだけど、やっぱり吊り目の超美形)
ストーリーもめちゃくちゃ面白いので、ぜひ一度読んでみてほしい。

他にも、花とゆめの『神様はじめました』に出てくる相手役(少女漫画のヒロインの相手役ってなんて呼ぶのが良いかしら?)も狐だった(ミカゲと言ってめちゃくちゃかっこいい狐)。

確か、ナルトも九尾の狐という狐にまつわる伝説からくる話だったはずである。
ナルトに詳しい方は、ぜひ教えてほしい。
この九尾の狐伝説は、中国発祥の伝説だが、栃木県の那須にゆかりの地があるので興味がある方は尋ねてみるといいだろう。

このような物語や伝説をはじめ、狐の嫁入り、狐にばかされた…など日本には狐にまつわる言葉が多く、日本人にとっては狐は特別な存在であるようだ。
話を稲荷神社に戻そう。
笠間稲荷神社は、菊まつりともなると参道に赤や紫といったカラフルな番傘がつられ、手水舎にはいっぱいの菊が浮かび、本当に素敵だった。


神社を散策していると、お手洗いの前に看板を見つけた。
“お稲荷さん”のご祭神はキツネではありません
最初は、神社内に大量にいる狐は、狐ではないということかと思って驚いたのだが、そうではなかった。
稲荷神社が祀っているものは、狐ではないという意味である。
いっぱんに「お稲荷さん」と言えばキツネをイメージされる方が多いようです。キツネはあくまで稲荷大神のお使いであって、神さまそのものではありません。稲荷大神にとってキツネは、熊野神社のカラスや八幡神社のハト、氏神さまの狛犬などと同じように「神使(かみのつかい)」「眷属(けんぞく)」などと呼ばれ、神さまのお使いをする霊獣です。
稲荷神社とおキツネさん- 笠間稲荷神社
「お稲荷さん 狐」と調べると、笠間神社のホームページが出てきた。
つまり、狐は神様の使いなのである。
さて、狐について掘り下げすぎた気がするが、今回は狐の話ではない。
本題に参りましょう。
いなり寿司と狐
稲荷神社は、漢字の通りお米がよくできることを祈って作られた神社。
そこの眷族(カミノツカイ)が、狐。
その狐の大好物が、油揚げ。
変わった趣味だよね。
狐って油揚げ食べるの・・・?
そんな変わった趣味をお持ちの狐さんにお供えするものとして、いなり寿司は生まれた。
狐が大好きな油揚げの中に、農耕の神である稲荷神がもたらしてくれたお米を入れたもの。
そう、それがみんな大好きおいなりさん(いなり寿司)なのだ。
我が家のおいなりさんは、薄めの油揚げに酢飯に胡麻を混ぜたごはんを詰めてつくる。
お正月くらいしか食べないのだけど、これが本当に美味しい。
シンプルな料理なだけに、家庭や地域によっても作り方が違うに違いない。
そう、今回の本題は、笠間のおいなりさんがくるみ入りかつ激甘だった話。
甘さマックス。くるみ入り。
笠間稲荷神社の前は、幾つものお店が並んで賑わっていた。
ふと目に止まったそのお店は、とても風流な佇まいで、そんな雰囲気に誘われるように中に入った。
何を売っているのか見てみると、胡桃稲荷の文字。
胡桃稲荷?
家に帰って袋を開けると、中に入っていたお箸袋にこのように書いてあった。
昔、笠間稲荷神社を建てる前、そこは胡桃林でした。それにちなんで笠間では、いなり寿司の中に胡桃を入れています。
なんとまあ!
そして、プラスチックのパックに詰められたおいなりさんを一口食べてみると、これがなんとも甘いこと。
甘い!あまーーーーーーーーーい!
こんなに甘いおいなりさんは初めて!
そして胡桃の食感がアクセントになって、不思議な味わいだった。
はじめは、おいなりさんの中に胡桃?!と驚いたが、意外に合う。
胡桃は味の主張が少ないので、酢飯にしれっと溶け込んでいたのだ。
私は甘いものがそんなに得意ではないのでたくさんは食べれなかったが、美味しかった。
やっぱり、食べ物は地域によって全然違うよう。
ちょっと離れただけで、こんなにも食べ物の味が違うなんて、とっても面白い!
皆さんの地域のお稲荷さんはどんな味ですか?
まとめ

笠間稲荷神社がとても立派だったので調べてみたら、日本三大稲荷神社の一つだということが判明。(なんでも三大まるまるがある気がする)
あとは京都の伏見稲荷神社(これが総本山)と、佐賀県鹿島市の祐徳稲荷神社。
茨城と京都と佐賀というのは良い離れ具合。(なんの具合?)
伏見稲荷は修学旅行で行ったことがあるが、おいなりさんは食べなかったのでまた行こうと思う。
佐賀の方も行ったことがないので行ってみたい。
笠間は、秋葉原から「やきものライナー」という長距離バスが出ていて2時間ほどで行ける。
やきものライナーという名の通り、笠間は笠間焼という焼き物も有名で、陶芸のワークショップや美術館があったりしてとても楽しい街なので、ぜひ行ってみてほしい。


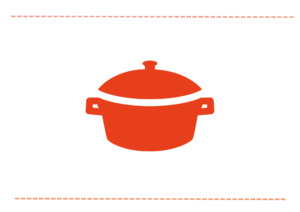
コメント